こんにちは!太宰府魅力発見塾塾長の福田です。
九州特に福岡の地名〇〇原(はる・ばる)と呼ぶのはなぜ?
●韓国では「原」をパル、ボルと読み、村や集落を意味していて、このパル、ボルからきているだろうといわれています。
地図の説明
新羅、百済、加耶(かや)(地図の赤丸、今の釜山)の位置がわかります。
金官加耶の右下の細長い島は対馬でその間の距離は50km

●663年の白村江の戦い(後述)のあと、敵国であった新羅は日本との友好を深めるために太宰府に来た時に白木原に滞在していました。
白木原(しらきばる)の地名の由来は新羅(しらぎ)からきているだろうといわれています。
●福岡の糸島にある可也山(かやさん)や芥屋(けや)も朝鮮半島の加耶(かや)からきているだろうといわれています。
例えば福岡では白木原(しらきばる)、前原(まえばる)、春日原(かすがばる)、熊本では田原坂(たばるざか)、大分は長者原(ちょうじゃばる)、長崎は世知原(せちばる)、佐賀は中原(なかばる)、宮崎は新田原(にゅうたばる)、東国原(人名 ひがしこくばる)、鹿児島は相原(あいばる)、旭原(あさひばる)、沖縄では山原(やんばる)などなど他にもたくさんあります。
●覚え方
地名はハルかバル
人名はハラ
●一方本州は小田原(おだわら)、関ヶ原(せきがはら)、米原(まいばら)、伊勢原(いせはら)などのようにわらやはら、ばらと呼びます。
●本州で原をばると呼ぶのは富山県に針原新町(はりばるしんまち)と針原中(はりばるなか)の二か所だけで九州からの移住者が開いた新地だと考えられています。
地名一つとっても九州は朝鮮半島との繋がりがいかに深いかがわかります。
因みに全国で地名を〇〇はる・〇〇ばると呼ぶのは99か所あり、そのうちなんと97か所が九州・沖縄。
福岡県27か所、佐賀県2か所、長崎県2か所、大分県24か所、熊本県11か所、宮崎県14か所、鹿児島県9か所、沖縄県8か所。
本州は上記富山県の2か所だけ。
(参考)
白村江の戦い
562年朝鮮半島の加耶(かや)が滅んで100年後の663年の白村江の戦い(唐と新羅VS百済と日本)で唐と新羅の連合軍に百済と日本の連合軍は大敗し、日本は唐と新羅の侵略に備え大宰府政庁(以下のブログ参照)を移転強化し、水城に水城堤(以下のブログ参照)や対馬に金田城(以下のブログ参照)などを築きます。
大宰府政庁跡
上記「大宰府政庁跡」にリンクで以下もご覧ください。
●水城堤(白村江の戦いの後、造った九州最大の防衛施設)
●鞠智城(きくちじょう)熊本菊池にあった大宰府の兵站基地
●金田城(対馬に大宰府防衛の最前線基地築城)
▶fukuda0917@yahoo.ne.jp
塾長より
いつも記事をお読みいただきありがとうございます。
もしよろしければ記事の一番下にある「コメントを残す」より
コメントを書いていただけますと、記事を書く励みになります。
これからも太宰府の魅力をお伝えしていきますので
応援よろしくお願いします。



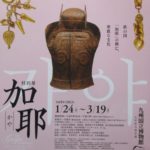

私の故郷、大分県日田市には、陣が原、元宮原などの地名があります。ばる、と読みます。日田市は盆地で山に囲まれていて、その内側の高台が、はると呼ばれてました。
石橋近さんコメントありがとうございます。日田でもそう発音するのですね。わたしも日田には4年ほど亀川に住んでいましたけど、その地名は知りませんでした。地名にしてもそれぞれの名前の由来を調べると面白いですね。
陣が原は、古戦場の跡と父から聞きました。
匿名さんコメントありがとうございます。「陣が原」をネットで調べてみたら「戦国時代に、大友義鑑(宗麟)が反大友勢と戦う為に陣を置いたのが由来」とありました。名前からして想像できますね。
東南アジアではパルとかパラではなかったですか。これは海洋民族の名残でしょう。半島からというより九州から半島へでしょう。
よしおうけいさんコメントありがとうございます。文化や言語は大陸から九州へ伝わってきているのでその逆で九州から半島へということならすごいことですね。
なるほど原をハルと呼ぶのは韓国語の集落を表す発音からきていたんですね。姓名に関してはハラと発音なのも納得しました。
KAKIHARAさんコメントありがとうございます。韓国と一番近い九州は昔から文化経済交流が活発で言語一つとってもその影響のほどが想像できますね。最近でこそ国交が正常化してきていますけどもう後戻りはしてほしくないですね。