こんにちは!太宰府魅力発見塾塾長の福田です。
念願の対馬にある太宰府の防衛施設だった金田城に続き熊本菊池の鞠智城に行ってきました。
鞠智城(きくちじょう)
長者館
地元の物産品販売。

温故創生之碑

防衛施設の配置図
左の赤い字が白村江、右下の赤い字は鞠智城

鞠智城・八角形鼓楼
鞠智城は7世紀後半(約1300年前)に大和朝廷が築いた古代山城です。
日本は友好国であった、唐と新羅の連合軍に敗北した百済を復興するため援軍を送りましたが、663年の白村江の戦いで唐と新羅の連合軍に敗北しました。
このため事態は急変し直接日本が戦いの舞台となる危険が生じました。
そこで九州には太宰府を守るために鞠智城(築年664年~667年の間?)、664年水城、665年大野城(福岡県)、基肄城(きいじょう、福岡県、佐賀県)、667年金田城(対馬)を築きました。
鞠智城築城の目的は
①これらの城に食料や武器、兵士などを補給する支援基地
②有明海から上陸する敵を見張る基地
他に瀬戸内海沿いの西日本各地(長門、屋嶋城、岡山に鬼ノ城など)に朝鮮式山城の防衛砦を築き、北部九州沿岸には防人(さきもり)を配備しました。さらに、667年に天智天皇は都を難波から内陸の近江へ移し大津宮を築き、ここに防衛体制は完成を見ました。
敷地には八角形建物跡2棟・総計72棟の建物跡が確認され壮大な施設でした。

築年月日は不明。664年~667年の間だと思われます。
最上階の三層目に置いた太鼓で城内に合図し時を知らせたり、見張りの役目を果たしました。
この八角形建物は国内の古代山城では他に類例がなく中国や朝鮮半島での文化の影響を強く受けていることが推定されます。
実際、同様の遺構は韓国の二聖山城(礎石建物)にも残っています。
八方位を宇宙の象徴とする道教の宇宙観の影響があると思われます。
高さは15.8m
「続日本紀」には文武2年(698)に「大宰府をして、大野、基肄、鞠智の三城を繕治(修繕)せしむ」との記述があるだけで、存続年代や、太宰府から70キロも離れた内陸部になぜ築かれたか、目的もはっきりしていない。(匿名さんのコメント参照)

柱跡が八角形に二重、三重に巡っています。
この遺構明示を行っている場所が実際に建物跡が見つかった場所です。

三層造りで一層目に49本(含む芯柱)、二層目・三層目に16本ずつの柱があり屋根の重みで建物本体ががっちりと支えられています。
中心部を突き抜ける芯柱は最上部のみで接合していますので「やじろべえ」の軸のようです。
そのために地震の際は揺れを吸収して絶妙のバランスを保つことができます。
そうすることで建物の倒壊を防ぐ塔建築の技術を再現しています。
この日は風を通すため扉が開けてあり、たまたま中を見ることができました。
中央が芯柱

一層目は柱が林立し人が立って歩く位の空間しかありません。

この建物には階段がなく必要に応じて梯子で上り下りするだけです。

一層内部の天井

庇(ひさし)


兵舎
板屋根造り。
1棟あたり50人の防人が寝泊まりしていた生活の場です。
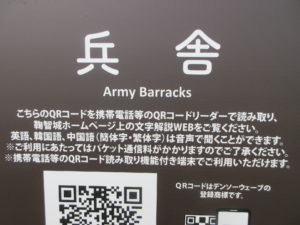
↓

米倉
校倉造りの高床式の建物で米などの穀物を保管。

↓

板倉
茅葺き屋根の建物。
武器などを保管。

長者山展望広場休憩所
とても景色のよい場所に建っております。

朝鮮式山城とは
いくつかの谷を取込むように,山の峰や斜面に石塁または土塁を築きめぐらした山城。特に朝鮮の三国時代に発達したことからこの名があります。

問合わせ先
温故創生館(鞠智城と同じ敷地にあります)
所在地:熊本県山鹿市菊鹿町米原443-1
開館時間:9:30~17:15
休館日:月曜日
TEL:0968-48-3697
PS
百済系銅像菩薩立像

平成20年10月23日貯水池跡池尻部から出土した銅像の菩薩像です。
ほぞを含む高さ12.7cm、幅3.0cm小型仏。
7世紀後半に朝鮮半島の百済で造られたと考えられており、百済の亡命貴族の指導で築かれたと考えられる「鞠智城」の歴史的背景を物語る貴重な資料です。(歴史公園鞠智城 パンフレットより)
想像以上に壮大な規模でした。
敷地には八角形建物跡2棟・総計72棟の建物跡が見つかっていることから、大宰府の防衛のための人数、日本から朝鮮半島へ1,000隻の船で約27,000人渡った兵隊の食料や武器の補給をしたことを考えると当然かもしれません。
663年白村江の戦い~667年の4年間に対馬から太宰府、中四国、都を難波から近江へ移し大津宮を築き防衛施設を造り上げたことは当時の天皇制、天智天皇の力の偉大さを知ることができると思います。
念願の対馬にある太宰府の防衛施設だった金田城に行き、鞠智城もまた太宰府の防衛施設だったということを初めて知りました。友だちにも知った人はほとんどいません。興味を持っておられる方もたくさんおられると思います。これだけのすばらしい歴史的遺産ですので全国へ向けもっともっと情報発信が必要だと思いました。
▶fukuda0917@yahoo.ne.jp
塾長より
いつも記事をお読みいただきありがとうございます。
もしよろしければ記事の一番下にある「コメントを残す」より
コメントを書いていただけますと、記事を書く励みになります。
これからも太宰府の魅力をお伝えしていきますので
応援よろしくお願いします。




詳しい説明のおかげで、城を築いたことを理解しました。ありがとうございました!
からつくんちさんコメントありがとうございます。
念願の金田城、今回の鞠智城とても勉強になりまた楽しかったです。
福田さん、いつもどおりのやさしい説明と写真でよくわかりました。鞠智城(きくちじょう)はちょっと読みにくいかなと思います。私も当日同行しましたが、本当にうまくまとめられています。見られた方は、現地で自分の目で見てみたくなるとます。
次が楽しみです。
四郎さんコメントありがとうございます。鞠智城とても読めませんよね。
早速読みガナ付け加えました。アドバイスありがとうございます。
その当時の歴史が少しづつ解ってきました。有難うございます。今後も色々な情報宜しくお願い🙏致します。
ふったろ-
ふったろ−さんコメントありがとうございます。わたしも少しずつわかってきました。わかってくるとまた次の疑問が湧きじっとしてはおれないようです。
私が興味があった事は以下の説明です。百済滅亡時期?の仏像が発見されました。
2008年10月、鞠智城跡貯水池底部の土中から宝珠捧持形菩薩像が出土
した。宝珠捧持菩薩像とは、長江下流域を勢力圏としていた中国の南朝で信仰
された仏像であり、南朝から仏教が伝えられた百済にもこのタイプの菩薩像が
みられる。不思議な持物を捧げ持つ菩薩は、死者の遺骨を供養する舎利供養の
姿を表現しようとしたもので、死者を弥勒菩薩の浄土である兜率陀天
とそつだてんに導く初期の観音菩薩をあらわしたものである。
鞠智城跡出土像は、百済系の仏像でも百済滅亡時の彫刻様式を伝えており、
亡命王族や高位な将軍の持仏として相応したとあります。
うっちゃんコメントありがとうございます。
早速ブログに鞠智城のパンフレットを参考に追加でアップしましたけどうっちゃんの説明の方が詳しいです。恐るべし一流コレクターうっちゃん!
仏像のアップありがとうございます。三年前、韓国から来日したイ・タウン教授の筑紫野市での歴史講座を拝聴しました。私が質問しました。「水城や大野城などの構築を百済人が技術指導した記録が朝鮮に残っていますか?」回答は「残念ながら日本で技術指導したとの古文書はありません」とありました。私の勝ってな推測ですが鞠智城跡出土像は、百済系の仏像でも百済滅亡時の彫刻様式を伝えており亡命した百済人が池に沈めて安寧を祈ったのではないかとーーー。奇遇ですがイ・タウン教授の奥さまは我が家の直ぐ側の太宰府市国分地区出身です。教授は10年程前に太宰府市役所で一次勤めていました。だから日本語は堪能です。
わたし当初菩薩立像はアップしませんでしたけど、さすがに専門家の観点は違いますね。改めまてうっちゃんの造詣の深さに驚きました。
素晴らしい、鞠智城特集。
この城に関しては、何の知識もなく徒然日記で触れ合うことができ感謝。
①菊池市では2019年10月20日に「鞠智城の日」を開催してました。
主催者は菊池市が「菊池市国営鞠智城歴史公園設置促進期成会」。山鹿市は「山鹿市国営鞠智城歴史公園設置促進期成会」と合同。大昔は菊池市も山鹿市もなく、多分大きい田園と豊かな米どころだったと想像できます。(今も変わらない財産でしょう)
②不思議なのは兵舎・米倉等として活用しても、太宰府から約80kmも離れた処に
何故ここなのかが歴史のロマンとして、誰しもが知りたいことと思いまして、転載しましたのでご参考までに。
産経ニュース[鞠智城 対「熊襲」の城が変遷?」(日本の源流を訪ねて)から
【前文略。しかし、歴史書をひもとくと、鞠智城をめぐっては多くの謎が浮かび、ロマンをかき立てられる。大野城など、ほかの古代山城は「日本書紀」に築造記録が残されているが、鞠智城の築造記録は見当たらない。「続日本紀」には文武2年(698)に「大宰府をして、大野、基肄、鞠智の三城を繕治(修繕)せしむ」との記述があるだけで、存続年代や、太宰府から70キロも離れた内陸部になぜ築かれたか、目的もはっきりしていない。
出土土器や瓦の検討結果から、存続年代は7世紀後半~10世紀中頃とされ、大野城などと築造時期も同時期というのが通説だが、県立装飾古墳館元館長の桑原憲彰氏は生前、鞠智城の3つの門がいずれも南向きなことに着目した。「熊本以南の隼人族、熊襲に対する前線基地の意味合いを持っていたのではないかと推測できる。大野城などより以前に築城され、白村江以後、山城としてリメークされたのではないか」との説を示した。
鞠智城をめぐる記述は平安時代に編纂された「日本三代実録」の「肥後国菊池郡城
院の兵庫(武器庫)の戸が自ら鳴る」との奇妙な記事を最後に、歴史から姿を消す】
鞠智城の歴史に万歳。
匿名さんコメントありがとうございます。すばらしい考察ですね。
当初は対熊襲のために築造が理解しやすいですね。
太宰府防衛施設のなかで築造年が何故この鞠智城だけがわかっていないのか不思議に思っていましたので。貴重な情報ありがとうございます。
鞠智城周辺広大で発掘進んでいる様子、写真でよくわかります、茨城の鹿島神宮、古代から鹿島立ちと言われ東日本の防人はここに戦勝を祈願して九州に向った由、一丸となりよく防衛しましたね。
若宮征之助さんコメントありがとうございます。
白村江の戦いは国を上げての戦いだったことがよくわかりました。対馬にも防人渡ってたようでした。貴重な情報ありがとうございます。
以前、菊池に行った時この鞠智城に行ったことがあり菊池ではなく鞠智とあること、城の作りが日本の城の型が違うこと異国の雰囲気を持ってる摩訶不思議??
…と、感じてました。
が謎が解けました!
昔の朝鮮半島との歴史や攻防を知ることが出来ました。
又、鞠智城の内部の柱や作り天井の作りも凄いですね。
興味深く見させて頂きました!
ありがとうございます。
天降川のタンポポさんコメントありがとうございます。
早くから鞠智城行かれてたんですね。わたしは対馬の金田城に行って初めて知りました。
何故八角形なのか不思議でしたけど行って理解できました。
また内部の構造はたまたま風通しで開いていたので知ることが出来とてもラッキーでした。
[…] 太宰府魅力発見塾大宰府の防衛施設だった熊本菊池の「鞠智城(きくちじょう)」https://dazaifumiryoku.com/private/15167/ […]