こんにちは!太宰府魅力発見塾塾長の福田です。
般若寺跡
所在地:太宰府市朱雀2-5



現地案内板
「太宰府市の朱雀地区、閑静な住宅街の一角にある『般若寺跡』は、654年孝徳天皇の病気が治るよう祈願するために、当時の太宰府の長官だった蘇我日向によって建立されました。お寺の跡地で、現在は塔跡の礎石が残されているほか、かつての寺域で、ここから東に100m離れたところには、鎌倉時代につくられた国の重要文化財である七重塔(後述)もあります」。

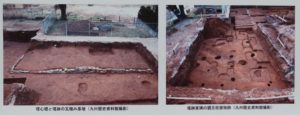
塔の心礎

般若寺跡 石造七重塔
重要文化財
「古代寺院の般若寺跡に建つ石塔。鎌倉時代後期に造立されたとされ、太宰府市で一番古い層塔です。花崗岩製で、高さは3.3mあり、台石には金剛界四方仏の梵字が刻まれています」。

般若寺跡と石造七重塔の石碑

七重の塔は重厚な稜線をもって囲まれ屋蓋の曲線美は華麗な容姿を示しています。

塔の四面にある各一文字は四方仏をあらわす梵字で、その書風は力強く刻まれ鎌倉時代の優秀な遺物であるといわれています。

●ここ般若寺跡は1586年の岩屋城の戦いで旧薩摩軍の本陣跡といわれています。
岩屋城城主 高橋紹運の首塚
薩摩軍の大将が高橋紹運の首実検をした後、般若寺跡近くに丁重に葬りました。

小高い丘のここからは岩屋城跡が正面に見え本陣としては最高の場所だったと思われます。
岩屋城跡(右端)

岩屋城城主 高橋紹運の胴塚
四王寺山中腹
高橋紹運は岩屋城の戦いで敗れたあと自刃し、薩摩軍に首をとられ残った胴を葬りました。

高橋紹運の菩提寺西正寺・胴塚・首塚詳細はこちら ↓
お問い合わせ・ガイドの依頼はコチラから
▶fukuda0917@yahoo.ne.jp
塾長より
いつも記事をお読みいただきありがとうございます。
もしよろしければ記事の一番下にある「コメントを残す」より
コメントを書いていただけますと、記事を書く励みになります。
これからも太宰府の魅力をお伝えしていきますので
応援よろしくお願いします。
▶fukuda0917@yahoo.ne.jp
塾長より
いつも記事をお読みいただきありがとうございます。
もしよろしければ記事の一番下にある「コメントを残す」より
コメントを書いていただけますと、記事を書く励みになります。
これからも太宰府の魅力をお伝えしていきますので
応援よろしくお願いします。


「般若寺跡と首塚、客館跡また菅原道真公の館跡、息子の隈麿の墓、娘の紅姫の供養塔」はこの一帯にあり徒歩での見学が可能です。駐車場はありませんので西鉄二日市駅から徒歩で10分足らずで行けます。西暦654年~903年(菅公没)までの歴史探索が楽しめます。
水城さんコメントありがとうございます。
そうですね。この界隈は政庁、菅公にまつわる史跡がたくさんありここだけでも結構楽しめますね。
お早うございます。改めて太宰府は、歴史の宝庫ですね。頭と胴と別々に葬るなんて残酷ですね。戦さは、昔も今のウクライナのように人命なんて無視されて、特に子供が犠牲になるのには、心が痛みます。平和が早く訪れるように願います。
チュウ臣蔵さんコメントありがとうございます。そうですね。特に戦国時代は首と胴を別々に葬っていたようですね。ロシアの蛮行を止める手立てはないものでしょうか。力が勝つのであれば動物の世界と同じになってしまいますよね。